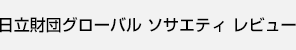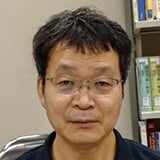アートと多文化共生社会
アートは多文化共生社会の期待に応えられるだろうか。本稿は,アートの試みが最大限に生かされ多文化共生社会に資するには,〈アートは見ればわかる〉〈知ればわかる〉といった神話を拒絶し,エデュケーショナルプログラムのなかで展示作品を体験することが不可欠であることを示す。さらにケアの考えから,共生関係をつくる場が必要であることを示す。
1. はじめに
「アートと多文化共生1」というとき,「多文化」と「共生」のあいだにあるギャップを,特殊多様でありながら普遍性をもつ2「アート」が橋渡しすると期待されているように感じる。実際,「アート活動や文化芸術を通じた在住外国人との共生の取り組み」で実績をあげているまちがある3。そうかと思えば,現代アートの大規模国際展において,多文化共生とは真逆の事態が生じていたりもする4。アートは多文化共生の期待に応えられるのか,考えてみたい。アート,文化5,共生という言葉で何を思い浮かべるかは人それぞれ,とりわけアートを定義するのは難しい6。そこでまず,アートを定義するのではなく,アートがどういうものと考えられているか,多文化主義がアートに関して引き起こしている問題を整理しながら確認する。その後,アートが多文化共生にどう貢献できるのかを,教育と関連づけて論じていくこととする。
2. アートにおける多文化主義
まずアートにおける多文化主義の問題点を先行研究([18], pp. 114-117)から整理し7(1)),その後アートがどのようなものと考えられているのか確認する(2))。
1)問題点の整理
(1)制作の問題(リュウ・ルーシャン氏)。(a)当事者性の問題:他文化地域におけるごく短期間の滞在制作でその地域や人々について言及してよいのか。(b)現代アートのわかりにくさの問題:文化的マイノリティをエンパワーすべき現代アートの表現形式がわかりにくいため,届けたい人に届かない。
(2)展示の問題(加冶屋健司氏)。西洋対非西洋という大雑把な区分を前提に,(a)非西洋文化の造形性のみに注目し本来の機能を無視してしまう。(b)ある特定の文化について,それがマイノリティ文化一般を代表しているかのように提示してしまう。(c)政治性と自律性の問題:政治的に正しいけれどアートとして「おもしろくない」と批判される。
(3)法的観点からの問題(志田陽子氏)。「個別の文化の主体として生きる人間が芸術家であれ,マイノリティであれ,その文化的な立場がどう尊重されるべきなのかを,他の文化的立場や制度とどのような関係を持っているのかを踏まえた上で,様々な観点から幅広く議論していくことが必要」。「近代的芸術観と文化的多様性とは齟齬をきたしており,かつまたその表現の背後に迫害や差別の問題の可能性が存在する時,その表現をどのように扱うのかは,既存のアートのリテラシーだけでは判断することはできない。」
(4)日本社会の問題(韓東賢氏)。日本社会では,そもそも多文化主義そのものが成立していない。
2)アートとはどういうものと考えられているのか
以上から,アートがどういうものかをめぐる,次の対比がうかがえる。
- 近代芸術/現代アート
- 純粋な自律性を志向する/政治や社会を表現する(人や背景を重視する)
- 造形性を重視する/文化的マイノリティをエンパワーする
- 既存アートのリテラシーで評価できる/他の文化的立場や制度との関係で評価する
ここに,
- 普遍性/多様性
- 感受するもの/理解するもの
という二項も加えることができるだろう。この「/」の両側のうち,左側は近代芸術の特徴,右側は現代アートの特徴となる。しかし両者は対立していない。左側つまり近代芸術は右側つまり現代アート成立の根拠になっている。
このことは左側にある「自律性autonomy」の意義を考えることで理解される。自律とは自分で自分にルールを与えること8。これを芸術にあてはめれば,芸術にルールを与えるのは芸術であり,その妥当性を判定するのは理性や知識ではなく感性である。近代芸術を支える近代の美学がこの自律性を確保したことの意義はとてつもなく大きい。たとえこの自律性が理念的なものであったとしても,である。なぜならこれにより,芸術は特定宗教の教義や政治の要求に従うことから解放されたからだ(もちろん無制限ではなく倫理などからの制約はある9)。
この自律性の考えは,現代アートにとっても支えとなっている。左側=自律性を拠り所に,アートの歴史を意識しながら,感性的に享受できる造形を通して,右側=マイノリティの文化的な立場がどう尊重されるべきなのかを考えさせるからこそ,それはアートと呼ばれるのである([13]も参照)。現代アートにおいても造形が重要なのはそのためである10。しかもいまや造形されるのは,木や金属といったモノだけではない。現代アートは,その歴史のなかで,造形の対象を,人と人,人と社会(含メディア環境)・自然の「関係」にまで拡張してきた[2]。この複雑な関係を感性的に体験可能なしかたで造形し,その体験を通じて「/」の右側にあるような事柄を考えさせるのは,至難のわざである。そこにアーティストの技術が求められる11。
非西洋の現代アートでさえ,それがアートを名乗るなら,この事情は同じである。したがって,西洋近代芸術を支える美学が現代アートの基盤にあることと,1)の(2)(a)のような西洋/非西洋(あるいはそれに相当する二者)のあいだにある不均衡な権力関係がもたらした制度的問題とは,別個に考えたほうがよい。たとえば,次の重要なテキストは,慎重に読まれる必要がある。
「〔前略〕ここで言う「アート」とは,従来,アイヌの造形表現を排除してきた西洋起源の大文字の「美術」,その制度とは異なる。むしろ,「アート」は,ひとりひとりの視覚や触覚(嗅覚や聴覚,あるいは味覚を喚起する作品もある)を通じた,きわめて個人的な行為,実践的経験を通じて生まれ,享受される。同時に,アートの創造は,制作を通じて意識的に過去を参照し,過去を読み換え,乗り越えて更新し,新たな社会認識,価値観を生み育む,公共性に富んだ行為でもある。それはむしろ,今日共有されつつある「現代アート」の概念に近い。」
[5], pp. 2-3
西洋起源の美術制度がアイヌの造形表現を排除してきたのは大問題である(他方で西洋起源の美術制度がなんでも都合よく美術に取り込んできたのも問題12)。が,それに続けて述べられている「アート」・「現代アート」の考えは,明らかに西洋起源の近代芸術,それを支える近代美学に基盤がある。とりわけ「ひとりひとりの視覚や触覚(嗅覚や聴覚,あるいは味覚を喚起する作品もある)」を通じて享受されるとある点はそうである。西洋近代の美術制度は否定されるが,近代美学の考えは生きている13。
大事なのは,そのアートが,ただ感じたり既存のアート・リテラシーを駆使したりするだけでは評価できず,他の文化的立場や制度との関係がわからなければ評価できないことだ。「制作を通じて意識的に過去を参照し,過去を読み換え,乗り越えて更新し,新たな社会認識,価値観を生み育む」過程は,作品を見ただけではわからない。
アートと多文化共生にとって危険なのは,「/」のどちらかだけを重視する立場である。左側を重視すれば,〈アートは見ればわかる〉という神話になり,右側を重視すれば〈アートは知ればわかる〉という神話が生まれる。さらにそれらの背後に〈アートには答えがあるものだ〉という神話がある。これらについては後述する。
以上,本節で確認したアートは,次のようなものであった。すなわち,それは,自律性を拠り所に,感性的に享受できる造形を通し,文化的マイノリティをエンパワーし,彼らの文化的な立場がどう尊重されるべきなのかといったことを考えさせようとするものである。
3. アートは多文化共生の役に立つのか
次に,こうした意味でのアートが多文化共生の役に立つのかを考えてみる。この問いは,アートが多文化共生そのものに役立つこととアートが多文化共生の〈教育〉のなかで役に立つことに分けて考える必要がある。
多文化共生のためのアートは,感受しうる造形を通して,それぞれの文化の特殊性,アイデンティティを明らかにし,そのうえで互いの存在を等しく認め合い,さらに共に生きるよう仕向けるのでなければならない。このとき,芸術の社会的機能([4], pp. 327-333)から,アートが多文化共生のためにどう振る舞うかを想像することができる。その機能とは,(1)教化善導,(2)弱者の武器,(3)炭鉱のカナリヤ,(4)視点変更,(5)視点創出,(6)異物である。簡単に説明する。
多文化共生は善いことだという前提にたち,これを大衆にわかりやすく伝えるのが(1),多文化共生の美名に隠された偽善や矛盾を指摘する,多文化共生のもとでマイノリティが置かれた現状を告発する,自らの文化的アイデンティティを相手の喉元に突き付けるというのが(2),作品が意図せずして来たるべき多文化共生を予示する場合が(3),社会の見方を変え多文化共生に目を開かせるのが(4),事物の新たな見方を創出することで多文化共生につなげるのが(5),鑑賞者によるいかなる解釈も拒むものが(6),である。
しかしながらたとえば,展覧会で何の説明もなく(2)の機能を果たす攻撃的な造形に出会うとき,その造形の単なる感受は,共生に目覚めさせる以前に敵対的感情を煽り,分断を結果するだけで,その歴史的背景にまで目を向けさせないかもしれない。また(4)の機能を果たすことを目指した作品も,視点変更のようなメタな機能を期待していない人(色や形を感受することだけに関心があり,なぜそのような色や形が用いられているのかについて考える習慣のない人たち)にとっては,なんの視点変更ももたらさないかもしれない。(6)に至っては,そのわからなさこそが作品の新しさかもしれないのに,わからないということに憤慨してその場を立ち去ってしまう人を増やすだけかもしれない。いずれも,〈アートは見ればわかる〉の神話に囚われている人たちである。
こうした懸念も,教育14においては,ある程度防ぐことができる。自身の文化の特殊性を訴えようとするあまり過激な表現を採用したり(誤解から過激な表現を採用している場合もある),あまりに特殊でその文化に属していない人が背景を理解できない状況が生じたり,ほんらい複雑な文化をひとつの要素で代表させてしまったりしているかもしれないとき,そこに適切な助言者がいれば,過激な表現が採用された必然性や,見ただけでは理解できない複雑な背景,その文化を構成している複数の要因,さらには自文化がいかに他文化から構成されているかなども,丁寧に説明することができるからである。
したがって,アートが多文化共生に資するためには,エデュケーショナルプログラムのなかで展示されることが必須となるだろう。これは強い意味で言っていることで,一般の展示ではなく,あくまで教育プログラムのなかで作品を体験してもらうのである。そうでなければ,アートが多文化共生の役にたつ可能性は,かなり低くなってしまうだろう15。
それはまた,作品が単なるプロパガンダもどき(すでに正しい答えを握っていると確信している制作者が,鑑賞者に制作者自身の信じる正解を受諾するか拒否するかの踏み絵的・二者択一的な態度表明を迫るもの)に陥ることを避けるためでもある。
加えてそのプログラムは,アートの読み解き方を教えるものとは異なっているのでなければならない。でなければ,〈アートは知ればわかる〉の神話に陥ってしまう。1990年代以降,巷間に溢れた「アート読解本」の弊害は大きい。造形を感受し,感受したものを自分で反芻し時間をかけて,必要な学習も行い他者と意見を交換しながら考え続けるからこそ,アートである必然性がある。読み解いて終わるような正解はない。
4. 共生
たとえ相手を理解したとしても,分離・並存に終わる可能性が高く,当事者性の問題も残ったままになる。そこからさらに共生へと踏み出すには,何かが足りない16。ここではそれを「ケア」と結びつけて考えてみる。
一般的にケアは,「ケアはケアする人とケアされる人の二人[以上]の関係」であり,「ケアされる人がケアを受け入れる(ケアしてもらっていると感じ,それに反応する)ことでケアは完成する」ものであり,「一方的なケアは不完全」である。さらに重要なのが,「状況や文脈に応じて発生し,内容が変わる」のがケアだ,という点である([6], p. 287)。この関係が成立していれば,一方が他方のかたわらに座っているだけでもケアである。
ここではもう少し強い意味で考えてみる。互いに互いをケアし,以前とは異なる自分,互いのいずれか一方だけに属さない関係が時間をかけてわずかでも生まれてくるとき,共生に入ったと考える。このような意味での共生へと踏み出すためには,関係をつくるための場が必要である。それは,他文化の作品を一方的に見る,あるいは,教育プログラムのなかで,それについて誰かの解説を聞きながら理解するだけでは生まれてこない。アートの枠組みのなかで,共になにかを制作するといった体験が,どうしても必要なのである。〈アートの枠組みのなかで,共になにかを制作する〉という言い方は誤解を招くかもしれない。それは,すでにあるアート作品と似たものをみんなでつくることではないからである17。
例をあげれば,文化的背景の異なる人同士が,互いに相手にわかりやすく自文化を伝えるメディアを制作してみた結果,その文化的背景も含め,伝えようとしている相手についての誤ったイメージと同時に自文化に対して自らが有していた先入観に気づき,共に愕然とするような場合である(参考として[24])。こうした〈共にする〉ワークショップには正解がない。そのため時間もかかるし忍耐も必要である。その過程で自分自身が崩壊してしまうかもしれない。こうした体験を,効率最優先の現代社会は許容しない。仕方がないので,正解がないなかでも何かを制作し続けることが社会的に認められてきた〈アートの枠組み〉を借りることになる18。だが,そうしたアートの枠組みさえ,もはや許容されなくなっている。それがなんらかの経済効果をもたらさない限り19。
5. おわりに
以上の手短な考察の結果,アートが多文化共生の期待に応えられるものなのか,という冒頭の問いには,どのように答えることができるだろうか。
優れたアーティストたちにより制作されたアート作品が,「差異によって分断がより一層高まるなかで私たちはどう生きていくのか,という極めてシンプルな問いを実践していくための共同的なリソースの宝庫」[22]であるというのは,その通りだと考える。しかしそれらをほんとうに宝庫にしていくためには,当然のことながら,それ相応の意識的な学習が必要である(言語の学習も含めて)。しかし多くの人にとり,そうした学習のための時間は限られている。いきなり作品を見ても,どうしていいかわからない。であるなら,教育プログラムとともに体験してもらうしかない。もはや多文化共生は自明なこととなった,などとはとうてい言えない事態が続いているアート業界の現状[18][22]に鑑みていまわたしが言えるのはここまでである。