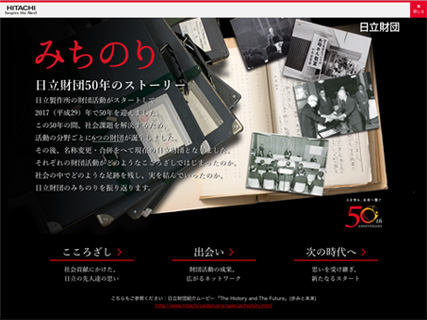シンポジウム・ダイジェスト



今、子ども全体の7人に1人、1人親家庭では2人に1人の子どもが貧困状態に陥っており、その貧困率はOECD加盟国34か国中、最も高い。それが今の日本です。子どもの貧困は、教育の格差を生み、子ども自身の人格や学力の形成のほか、定職に就けないなど、その後の人生にも大きく影を落とします。また地域社会にとって貧困は非行や犯罪の引き金ともなり、不安を増大させたりもします。こうした問題に対処するために社会保障費など税金投入が増大する一方、働かない若者の増加により税収が抑制されます。つまり、子どもの貧困や教育格差は、その家庭だけでなく今後の日本社会全体にとっても大きなリスク要因となっているのです。
今回のシンポジウムでは「子どもへの投資が明日をつくる─教育と社会的リターン─」をテーマとして、未来の子ども、家庭、地域社会、そして日本全体が豊かに、幸福になるためにはどうすべきかを考察しました。
まず基調講演として、1男1女の子育ての毎日を明るく、そしてリアルに描いた漫画「毎日かあさん」の作者、西原理恵子さんをお招きし、親も子どもも幸せになれる子育ての考え方や方法についてお聞きしました。さらにシンポジウムは、下記の4講演を行いました。慶應義塾大学総合政策学部准教授の中室牧子氏より、教育経済学者の立場から貧困や教育格差が個人や社会にもたらす経済的損失と、その解決に向けての提言を頂きました。
続いて日立財団Webマガジン「みらい」編集主幹であり、拓殖大学政経学部の守山正氏より、犯罪学の見地から、貧困と犯罪についての関係性、その歴史と現状、さらに解決策についての考察がありました。教育評論家として活躍されている親野知可等氏からは、将来、生きる力のある子どもに育てるために、その具体的な方法についてのお話がありました。
最後に、貧困に苦しむ子どもたちに無料の教育支援を行っている渡辺由美子氏からは、子どもたちの貧困の現場での状況と、教育支援の意義や効果について説明していただきました。いずれの講演も子どもの貧困や教育格差を根本として、その内容が密接に関係し、層の厚いシンポジウムとなりました。講演録全体に目を通していただくことで、この問題に対しての課題や解決の方策が浮かんでくるはずです。
日立財団では今後もこの問題に関わり、日本の未来を少しでも良くするために尽力していきます。
基調講演 講演録
シンポジウム
講演録1
貧困の世代間連鎖を断ち切る - 教育経済学の研究蓄積から -
経済的な状況が良く、勉学に対する意欲が高い子どもと、
経済的な状況が困難で、意欲が低い子ども、この2パターンに分かれる。
准教授 中室 牧子 氏

准教授 中室 牧子 氏
講演録2
非行と貧困 - 格差社会における社会的排除 -
非行現象にはこれまで「波」があり、それは4つある。
拓殖大学政経学部
教授 守山 正 氏
講演録3
親力できまる子どもの将来
居心地が良い家庭は、共感的な家庭です。
親野 知可等 (おやの ちから) 氏
講演録4
貧困の連鎖と教育支援
1人親世帯のお母さんの8割が働いている。それでも貧困。
理事長 渡辺 由美子 氏
「人づくり」は日立財団のDNAです。




日立財団では、その活動のひとつとして「人づくり」に注力してきました。それは当財団の前身、「(財)小平記念日立教育振興財団」と「(財)日立みらい財団」が昭和40年代から連綿と行ってきた各種施策を源流としています。当時の財団が目ざした「幼児(早期)教育」や「青少年の健全育成」は現代の成熟社会においてさらに重要度を増しています。財団創設50周年を節目に今一度原点に立ち返り、現代、そして未来を視野にした文脈で「人づくり」を見つめ直していきます。
「人づくり」を目ざした私たちの先達

『幼児教育しかも、躾教育が成人した後の人格を形造ると考えると社会をよくするにはこれが一番大切だと思います』
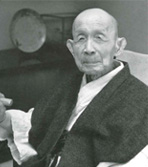
『青少年が人生を踏み迷うことなく強く生きぬいていくためのお手伝いをしたい』
日立財団50年のストーリー「みちのり」