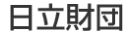特別インタビュー
課題と対策
日本政府いちばんの少子化対策は、働き方改革

田中:おっしゃるように、個人の願いや希望が叶う社会でありたい。しかしその一方で社会的、経済的な問題も顕在化しています。人手不足で働き方改革がなかなか思うように進まなかったり、労働人口の縮小で年金制度の維持が難しくなってきています。こうした課題の解決に、少子化問題の対策が効果的だと私は思います。日本はグローバルで見ると特殊な社会ですが、良い文化や人間性を持っているので、そういう状況を維持するためにも人口が増えて、これからもグローバルに存在価値のある国でありたいと思っています。

白河:本当に人手不足がすごいですよね。いま赤ちゃんが生まれても働くのはだいぶ先になりますけど、少子化対策にはしっかりと取り組んでいくべきです。日本では昭和の高度成長期に発展して現在も活動している企業が多いですが、その頃のやり方、働き方が今なお残っている状況ですよね。あの頃はテレビだったらテレビをたくさん作ることが市場で勝つ秘訣だったので、工場もなるべく長時間動かして、しかも筋肉質な男性が働いてくださることが条件だったのですよね。そうなると女性は家で家事や育児を中心にする、そこには経済的な合理性があったわけです。しかし、状況は変わりました。
田中:確かにそうですね。
白河:昭和の高度成長期のような勝ち方とか、モノのつくり方をやっていた時は、実は均一な集団のほうが強かったですね。いまはそうではない。ビジネスにしても暮らしにしても、女性のようにビジネスの世界ではマイノリティだった人たちの存在や意見がとても大切になってきています。人口動態と共に時代は変わるということを非常に感じますよね。
田中:人口動態プロファイルは会社組織などさまざまなところまで影響しているので、かなり重要ですよね。現在の出生数、出生率を上げる必要があると私も思っています。この対策として先生は、例えば企業や社会でどんなことが必要とお考えでしょうか。
白河:日本政府のいちばんの少子化対策は働き方改革で、労働時間上限がついたことだと私は思っています。やっぱり人が持っている時間には限りがあるので、それをどう使っていくかというところを初めてみんなが考えましたよね。企業も社員の時間は有限であることに気付きました。生産性高く働いて自分の時間、やりたいこと、生き方も大事にしてください、という方向にどんどん変わっていますよね。その中に、例えば結婚とか子育てとか勉強とか介護、また留学に行ったりする人も増えています。そういうことがすごく重要と思っています。私が取材した人で、婚活中の女性が「働き方改革って本当に進んでいるんですね」とびっくりしていました。理由を聞いたら、お相手の大企業の40代ぐらいの男性が「17時に会いましょう」って言っていたそうです。
田中:昔だったらそんなに早い時間からデートなんて考えられなかったですからね(笑)。そんなところにも働き方改革の効果が現れているのですね。
白河:政府のデータによれば、男性が家事・育児に参加する時間が多いと、第二子が生まれる確率が増えるそうです。第一子のとき、夫が家事や育児に参加する時間が0時間という家庭は、その後11年間追いかけても1割ぐらいしか第二子は生まれていませんでした。共働きでもそうでなくても結果は全く同じです。一方で、週に6時間以上、夫が家事や育児を担当していた家庭は、その後7~8割ぐらいの確率で第二子が生まれています。世界的に見ても男性の家事・育児の参加率の高い国は、少子化はさほど進んでいないというデータもあります。

田中:私もそれは聞いたことがあります。厚生労働省の方が示された資料で、残業時間と第二子の出生率は非常に相関があり、残業時間の少ない人は出生率が高いという。あのデータは印象的でした。
白河:残業しないから、その時間は家事や育児をしているかというと微妙なところですけど(笑)。都道府県別のデータでもはっきりしていて、週60時間以上働く人が多い都道府県は少子化の傾向があります。通勤時間も非常に関係があります。通勤時間が長い県、特に神奈川県が顕著で通勤に2時間ぐらいかかったりしていますが、それと少子化は連動しています。もう一つ、女性が子供を持って働けるかどうか。これも相関があります。男性がパート・アルバイトだと結婚の確率が低いから、まずは男性の施策をしましょうとよく言われますが、調べてみると男性のパート・アルバイトと結婚との相関はあまりないという結果が出ています。それよりも働く時間、働きやすさの方が、結婚や出生率と関連しているはずです。
田中:働く時間は、結婚や子育てに非常に影響しているということですね。
白河:働く時間というか、自分の時間がどのぐらいあるか、ということだと思います。
田中:企業としては、働き方改革でなるべく会社にいる時間を減らすことをしていますが、それを追求していけばいい、ということでしょうか。
白河:会社が利益を上げないと意味がないので、まず生産性高く働いていただいて、長時間いることだけが評価の対象ではないという風潮ができること。そうしたら、次に働き方の柔軟度を高めていくと良いと思っています。それこそ場所や時間にあまりとらわれない働き方、それが浸透していくと働くことと家事や子育てはすごく両立が進みますよね。
田中:なるほど。働くことの効率と柔軟性の追求ですね。
白河:いまの若い人たちはさまざまなことを考えていて、そのひとつに「両立不安」があります。ある会社の調査で、子どもがいない働く女性の92%ぐらいが、将来子どもが生まれたときの子育てや家事と仕事を両立させることに対して不安を感じているのです。もし、自分がそうなったらどうするか、この質問に対して「何かを諦める」と回答しています。では何を諦めるか、その一つが仕事で両立不安を解消するために退職・転職を考えたことがある人が40%にものぼっています。これでは、せっかくの人材がいなくなってしまいます。その一方で、プライベートを諦めるという方法もあるわけです。それはつまり、妊娠・出産を遅らせることで、この調査ではそれを経験したことがある人は50%以上になります。しかしこればかりは、個人差はありますが時期があることで、少子化問題を考えると得策ではないですよね。
田中:そういう両立不安の不安要因を取り除いていくこと、そのためのアクションがこれから重要になっていくのでしょうね。
白河:こんなに多くの人が両立不安を感じているんだ、と私もその結果を見て驚きました。せっかく良いところに就職できて、好きな仕事に邁進しているのかと私は思っていたのですが、最近の若い人たちは違いますね。先輩たちの動向を見て、いろいろなことを考えています。ですから社内のかたたちが、男性も女性もいきいきと子育てをしたり、共働きがしやすい環境になると、後輩たちもそれを見てものすごくモチベーションが上がるはずです。「ああいうふうに将来なれるなら、いま頑張ろう」とか。そういうモチベーションを持つことは、少子化の対策としてもすごく大きいと思っています。