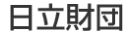特別インタビュー
対策の実例
フランスでは、子育てで何かを犠牲にしていません。
田中:少子化対策の具体例を教えていただけますか。
白河:三重県では、県を挙げて「日本一のワークライフバランス県になる」を標榜して、各種の取り組みを行っています。そのあとに国の働き方改革政策が始まったので、働き方改革も率先してやっています。
田中:国の政策より前にやっていたわけですね。
白河:そうです。ワークライフバランスの実現に取り組んだのは早かったです。いまは三重県庁の職員だけではなく、地元の企業のかたたちともシンポジウムを開催したり、県の予算でコンサルタントを導入したりして取り組んでいます。そうすると3年目ぐらいから、出生率がここ20年間で一番上がったそうです。いまは知事の発案で、県庁では男性も子供が生まれたら2年間の育児参画計画書を提出することになっています。つまり男性も育児に参加する。働き方も変わるということを見える化したわけです。男女平等もすすみ、男性で育児を積極的にしたい人は非常にやりやすくなるでしょう。

田中:確かにその取り組みは良いですね。それに、先ほどの保育園の送り迎えのように、育児や家事に対して、以前よりは「そうしなきゃいけないよね」という気持ちを持つ男性が増えたというか、心のハードルが少し低くなったような気がしますね。
白河:その「心のハードル」が見えないバイアスなんですよね。この「心のハードル」を取ってくださるということに関しては、企業の上層部のかたたちの理解がすごく大きいですね。実は簡単なことで、上の人が「育児休業を取れ」と言ったらみんな取るのです。銀行業界は今、男性の育児休業に業界を挙げて取り組んでいます。そうすると去年の育休取得はひと桁のパーセンテージだったのが、あっという間に79%まで上がった銀行もあります(笑)。上層部の指示は皆さんしっかり従いますので、簡単に上がるのです。そしてこのことがだんだんと当たり前になってくると、まだそういうことがない人、若い人たち、特に女性は勇気づけられますよね。それに夫もゾンビにならないで、ちゃんと育児や家事をやるようになります。この取り組みをされた銀行のかたが「50%を超えると、育休を取るものなんだとなる」とおっしゃっていました。いままでは「取ったらまずいもの」という空気だったと思うのですが。そういう努力ははすごく大きいと思います。
田中:そういう具体的なことから始めていけば、もっといろいろなことが可能になってくる感じがしますね。
白河:あるメーカーの女性で、研究職のかたが「働き方改革のおかげで第一子と第二子のときでは全く違う」ということをおっしゃっていました。「昔はここまでやりたいけどちょっと無理かな」と諦めることがあって、それはプライベートでも同じでした。でも最近は、「仕事もプライベートも諦めなくてよくなりました」と言うのです。で、最後に「いま2人子供がいるけど、この働き方が昔からあったら子供をもう一人産んでいたかもしれない」と言ったのです。これはすごい話ですよね。いきいきとして、限界を感じないって、幸せなことですよね。そういう人が一人でも増えることは、企業にとっても社会にとってもすごい財産だとも思いますし。働くことでも、家庭でも、個人の希望が叶えられていって、それが少子化の解消につながるというのが、これからのあるべき姿だと私は思っています。
田中:確か、フランスは出生率が低かったけど、改善しましたよね。
白河:そうです。1960年代ぐらいから一気に改善しました。
田中:どういう対策を行ったのでしょう。
白河:とにかく、子育てで犠牲になるものがないようにしましたね。出生率が低下したときに、女性に対して「子育てと仕事、どちらを選ぶか」という統計を取ったところ、仕事を選ぶことが分かってしまったのです。あの国は皆さん自立していますので、誰かに養ってもらうという考え方がないからなのですね。仕事がないとごはんが食べられなくなってしまう。じゃあ、仕事を選ぶのだったら、子育てをしても、仕事のほうに支障がないようにしないといけない、ということで、育休を取っても同じ部署、同じ仕事に戻れるといったさまざまなルールを作って、子育てで女性が犠牲にならないような仕組みを作ったのですね。この支援によって、女性は子供が生まれても失うものはなくなりました。予算も日本の3倍ぐらいは子育てにかけていますので、例えば公立大学の学費は無料になっています。これは大きいですね。
田中:女性が犠牲になることがないように、というのはいいですね。
白河:あちらでシングルマザーのかたにインタビューをしたとき、経済的には厳しい生活をしているはずなのに、すごくおおらかで楽しそうでした。高校生の娘さんをお持ちのかたで、その娘さんの進路に関して非常に明るく語っていたのが印象的でした。そんなふうに将来に対して希望を持って語るシングルマザーがあちらでは多かったですね。日本との違いもかなり感じました。あちらは、お金がなくても子育てはなんとかなるのです。女性が働いて子育てすることは大変ではない、なんとかなるという意識があり、産んで育てる空気がすごく醸成されている。最近はさらに進んで、男性の産休を2週間取ってもらうようにしました。企業が3日間、政府が11日間のコストを負担する完全有給です。その14日間の産休を、7割の男性が取っています。「父親のための休暇」という名前で、その14日間を奥さんと赤ちゃんと三人で一緒に過ごします。フランスでは出産後すぐに病院から戻ってきますし、里帰り出産もないですから、出産後すぐに夫妻と赤ちゃんだけで過ごすわけです。育児のスタートアップを一緒にやるための休暇ともいえます。そしてその2週間を過ごすと、男性のほうも子育てに対するコミットが強くなる。ゾンビ化しないんです。
田中:スタートが大切だというわけですね。

白河:そうです。最初から関わることが大切です。私の友人もフランス人と結婚して向こうに住んでいて、その14日間の最初の日、夫は全く無関心だったそうです。それで彼女は泣いて怒って、大ゲンカするところからスタートして、その14日が終わる頃、夫が先に仕事場へ行くことになったとき、「本当にごめんね、先に出かけけるけどごめんね」と言って会社に行きました。態度がその14日で全く変わったわけです。フランス政府の頭の良いところは、男の人は子供が生まれただけではパパにはならないということを見切って、そこに政策を入れてきた。そこがすごく興味深いです。北欧、フランスでは結婚しないで子育てするカップルも5割以上です。政府はお金も使い、緻密に制度設計したりしています。そうして、子どもを持ったことの罰ゲームは一つもないようにしています。
田中:子どもを持つことの罰ゲームとは、どんなことでしょうか。
白河:日本は罰ゲームが多いですよ。保育園に入れないとか、保育園でおむつを持って帰らないといけないということが、少し前フランス在住のジャーナリストの人が問題視して運動を始めました。紙おむつの場合、日本の保育園で廃棄しようとすると産業廃棄物扱いとなってお金がかかるのです。現在は無料になったところが多いですが。そこでお母さんが名前を書いて、汚れたおむつを持って帰らないといけないということになっている保育園が現在も多くあります。フランスでは手ぶらで保育園に預けるそうなのですよ。あちらで子育てしている人に言わせると、「日本は保育園に大荷物を持って行かないといけないし、名前も書かないといけない。最後に臭いおむつも持って帰れとはなにごと? 感染症とか怖くないの」。日本って、働き方もそうですが、「よりがまんした方が勝ち」みたいなところがありますよね。我慢したり、犠牲を払った人が最後は周囲から認められるようなことがありますが、子育ても同じ。がまん競争というか、罰ゲームみたいなところがいっぱいあって、耐えて完走したら勝ちみたいなところがあるので、子育てに関しては喜びだけでなく苦難も大きい。その苦難をなるべく社会が軽くしてあげることが、これからは重要ですよね。